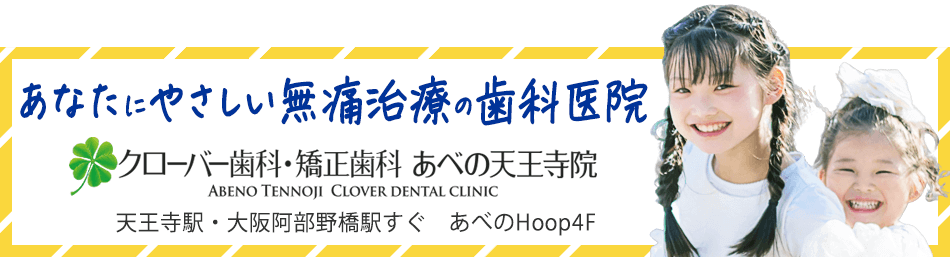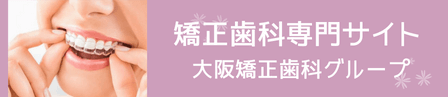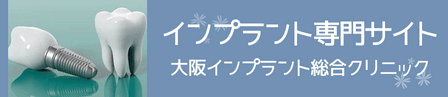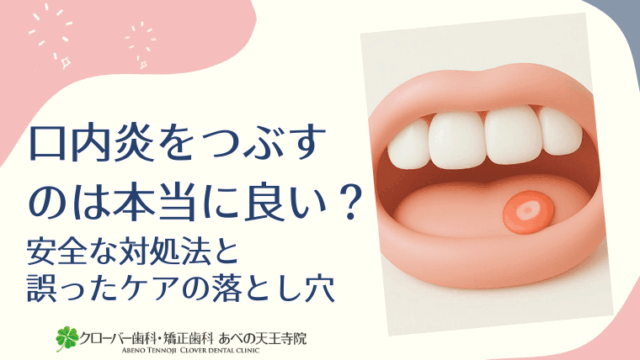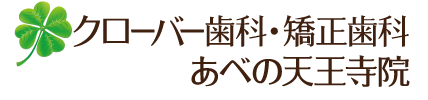歯を失う理由をおしえて

クローバー歯科・矯正歯科 あべの天王寺院 歯科医師 永井 伸人
歯を失う原因は多くありますが、一つだけの原因ではなく、幾つかの原因が重なった結果、歯を失ってしまうケースが多いです。抜歯が必要になる、歯が抜けてしまうなど、歯を失う主な原因をご説明します。
歯の喪失の原因とは?
1.歯周病菌による感染
歯周病になる原因は、歯垢(プラーク)と呼ばれるネバネバした歯への付着物の中に生息している歯周病菌への感染です。
歯垢は歯磨きが不十分で汚れが取り切れていない場合や、糖分を含んだ食べ物や飲み物をたくさん摂った時に増えていきます。
歯周病は歯肉炎と呼ばれる歯茎の炎症から始まりますが、重症化すると歯茎だけでなく歯を支えている骨が破壊されて歯が抜けてしまうこともあります。
2.虫歯菌による感染
虫歯が進行して歯に大きな穴があき、虫歯菌によって歯の根まで溶かされた場合や、歯根にまで虫歯菌が進んでしまった場合には、抜歯しなければなりません。
虫歯を予防するために、毎日の歯磨きなどのセルフケアで歯垢をしっかりと落とし、歯医者の定期健診を受けて歯石を除去しましょう。
3.噛み合わせの悪さ
歯が正しい位置で噛み合っていないと、特定の歯に大きな負担がかかってしまいます。その状態でずっと噛んでいると、歯が欠けたり、被せ物や詰め物が取れたり、虫歯や歯周病になりやすいというリスクもあり、歯が抜けてしまうということに繋がります。
正しい咬み合わせに調整することで、歯を長持ちさせましょう。
4.悪習慣(歯ぎしり・食いしばり)
歯にダメージを与える悪習慣として、歯ぎしり、食いしばり、噛みしめがあげられます。これらの癖があると、噛み合わせが悪い場合と同じく、奥歯に大きな負担がかかり、歯周病のリスクが高まります。
ナイトガードを利用して就寝中の歯への負担を減らしたり、日中も歯を食いしばっている時間を出来るだけ減らせるように、顎の力を抜くことを習慣づけるように
ナイトガードを使用したり、歯を食いしばっている時間を減らせるように意識的に顎の力を抜くなどしましょう。
5.のう胞、腫瘍
のう胞とは、体内に生じる袋状のもののことをいい、何らかの病気によって生じるものと原因不明で起こるものがあります。
お口の周辺に出来るのう胞や腫瘍は、あごの骨の内部や口の粘膜に出来ることがあります。
歯根や歯の組織などにのう胞や腫瘍が出来た場合は、歯を抜歯しなければならないこともあります。
6.転倒などの外傷
転倒や強くぶつかった時などの衝撃による外傷で歯が欠けたり、グラグラになったり、歯の位置がズレることがあります。外傷の程度によっては抜歯が必要になることもあります。
歯を失う理由に関するQ&A
むし歯と歯周病が歯の喪失の二大原因とされています。これらの病気が進行すると歯が弱くなり、最終的には喪失する可能性があります。
抜歯の主な原因は「歯周病」(37%)、次に「むし歯」(29%)、その次は「破折」(18%)です。このうち「破折」の多くはむし歯由来で、その割合を加えると「むし歯由来」は47%となり、最大の原因となります。
喪失リスクの高い歯は未処置のむし歯、クラウン(冠)装着されている歯、部分義歯の針金がかかる歯(鈎歯)、歯周疾患が進行している歯です。
歯の喪失を防ぐためには、どのような原因で歯が失われていくかを知ることが必要です。また、早期にむし歯や歯周病を治療し、根本的なダメージを防ぐことも重要です。
まとめ
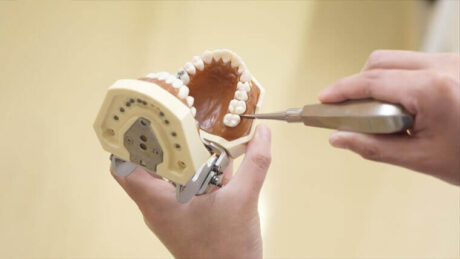
歯を失う原因についてご説明しました。予防策や対処法がある場合は、事前に予防策を講じることが歯の長もちに繋がります。