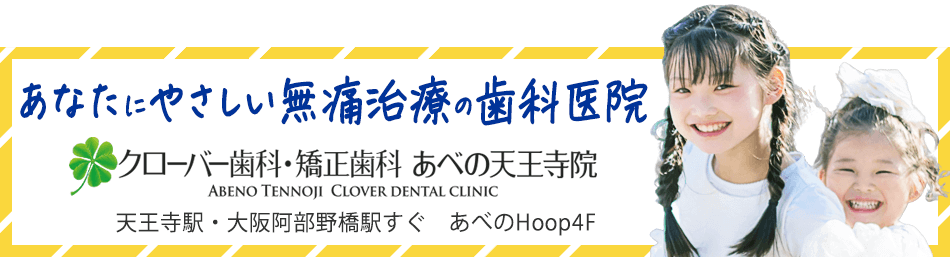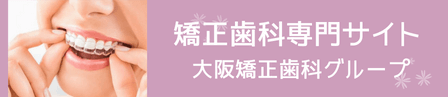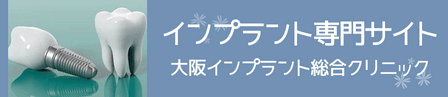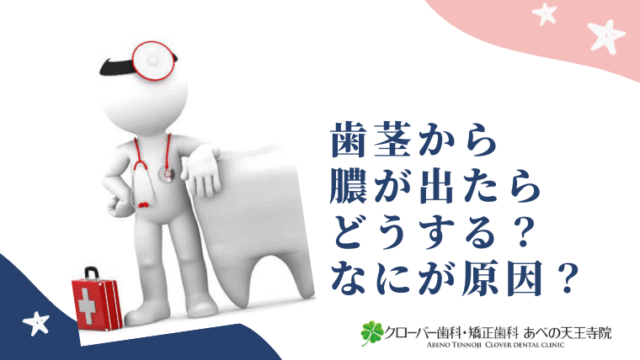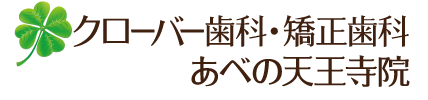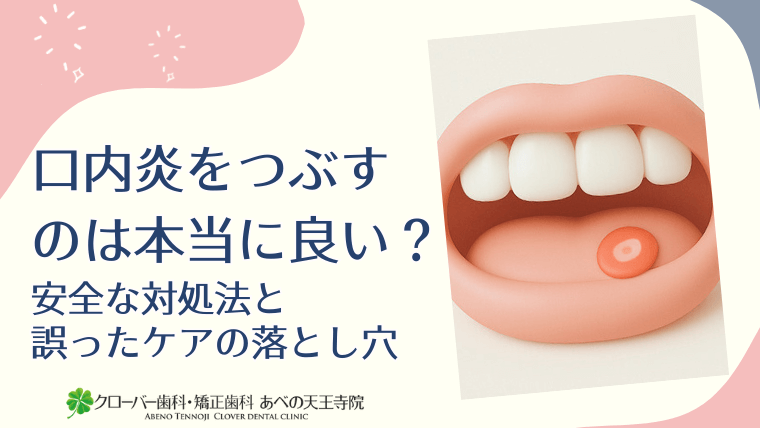
口内炎はつぶすほうが良いと聞いたけど、本当にそうなの?と実際に鏡を見て不安に思われる方もおられるでしょう。口内炎の実態、つぶすことによってなにかリスクがあるのか、長い口内炎は注意すべきことがあるかなど詳しくご紹介いたします。
目次
口内炎とは何か?
口内炎とは、口腔の粘膜に生じる炎症の総称です。唇の内側や頬の内側、舌、歯茎、上顎の天井など、口の中のさまざまな粘膜部位に発生する炎症を指します。原因は一つではなく、疲労や栄養不足、免疫力低下、外傷、ウイルスや細菌の感染などがあります。 典型的な症状としては、ヒリヒリとした痛みを伴ったり、飲食や会話の際に刺激を感じるため、早く治したい、痛みをなんとかしたいと思ってしまいがちです。
口内炎の種類
口内炎には様々な種類があります。白く丸い潰瘍ができるアフタ性口内炎、粘膜全体が赤くただれるカタル性口内炎、ウイルス性、真菌性、アレルギー性のものなどです。そのため、口内炎はつぶせば治るという単純な図式ではなく、原因や症状によって対処が異なるということをまず押さえておきましょう。
口内炎をつぶすってどういうこと
一般に口内炎をつぶすという行為は、次のようなものを指します。
- 爪、指、針、ピンなどで、白く盛り上がった炎症部や水疱状や血豆状のものを潰して中の液や血を出す
- 水ぶくれ、血豆、盛り上がった粘膜部位を早く治るだろうと自分で破り、裂く
- 痛みが強いので液を抜いたら楽になるかもと思って、無意識に噛み潰したり噛んでしまう
誤解も一因
なぜ口内炎をつぶす行為をするかについては、いくつかの誤解や感覚が背景にあります。
- 中に溜まっている液体を出せば早く治り痛みがマシになるかもしれない
- 見た目が気になるから何かしたい
これらの気持ちから、つぶす行動に出ますが、実際には根拠が乏しく、むしろ逆効果となる可能性が指摘されています。口内炎をつぶすというキーワードで検索される背景には、つぶしたいけど良いのか?という疑問や不安もあるわけです。
口内炎つぶすことで起きるリスク
口内炎をつぶすという行為は、短絡的には治りが早くなるかもと思えても、実際にはこのようなリスクがあります。
細菌やウイルスの侵入リスク増大
口内炎が起きている部分の粘膜はすでに傷ついていてただれている状態です。ここをさらに自分で破ってしまうと、外部から細菌等が侵入しやすくなり、感染を起こし悪化したり、治癒を遅らせたりするリスクがあります。
傷が深く広くなる可能性
潰すことで粘膜の壁が壊れ、炎症部位が広がったり、癒着や硬化を起こしてしこりになったり、跡が残ったりするケースもあります。
痛みや出血、治癒遅延
潰した瞬間はスッキリするように感じても、かえって刺激を増やしてしまい、痛みが長引いたり出血を伴ったりすることがあります。
別の疾患を見逃すリスク
口内炎だと思ってつぶしたが、口腔がんなどの別の病気が隠れていたというケースも報告されています。口内炎が長引いたり、頻発したり、形状や色が異常な場合は自己判断せず医師にかかり、相談すべきです。
口内炎をつぶすという行為には明確なデメリットがあり、良い習慣とは言い切れません。むしろ止めておいた方が安全です。
正しい口内炎のケアや対処法
では、口内炎をつぶす代わりに、どのような対応をすればよいのでしょうか。
口腔内を清潔に保つ
食後や就寝前に丁寧に歯磨きし、うがいを行い、刺激を最小限にしましょう。粘膜の周囲を柔らかめの歯ブラシなどで磨くようにし、粘膜自体を無理にこすらないようにしてください。
痛みや刺激を避ける
熱い、辛い、酸っぱい、硬い食品は、口内炎の部位を刺激するため避けるのがおすすめです。タバコやアルコールも粘膜を弱める原因となるため控えると改善が早まる場合があります。
栄養や休養をとる
粘膜の修復には、ビタミンB群(特にB2・B6)、ビタミンC、亜鉛などが関与しています。バランスの良い食事を心がけましょう。また、睡眠不足やストレス、疲労があると免疫力が下がり、口内炎ができやすく、治りにくくなるため、休養をとることも重要です。
市販薬やパッチの活用
軽度の口内炎であれば市販の口内炎用軟膏、貼付パッチ、スプレータイプなどを使うことで痛みの緩和や治癒促進が図れます。貼るタイプは患部を保護しながら治療成分を届けるため、食事の際に誤って噛んで潰してしまうリスクも減らせます。
原因の除去、刺激の改善
入れ歯や矯正器具、歯の尖りなど、口腔内の物理的な刺激がある場合には、それを調整してもらうことで再発予防になります。
つぶす以外でできる対処方法をきちんと行うことで、口内炎の治癒を促し、悪化を防ぐことができます。
つぶしたらどうなる?注意点をおさらい
つぶしてしまった、もしくはつぶれた場合、またつぶしたい衝動がある場合にどうすべきでしょうか。
自分でつぶしてしまった時
もし口内炎を潰してしまった場合は、出血、汁、血液が出ても慌てず、口腔内を清潔に保つことが最優先です。うがいや歯磨き、なるべく刺激の少ない歯ブラシで周囲をケアし、細菌感染を防ぎましょう。痛みや腫れが増したり、出血が止まらないなど異変があれば早めに受診を考えましょう。潰したために早く治ると期待するのではなく、むしろ治りが遅れたり状況が悪化するリスクがあることを理解しておきましょう。
潰したいという衝動がある時
この見た目を早くどうにかしたい、液を出せば楽になるかもしれないという気持ちが出ることがありますが、触らない、つぶそうとしないという意識を持つことが重要です。代わりに、冷たい食べ物、飲み物、貼るパッチ、柔らかい食事など、刺激を減らす手段を取るとよいでしょう。
何度も触ったり、いじるクセがある人は、寝る時にマウスピースを使って食いしばりを防ぐなど口腔内への刺激を減らす工夫を検討することもあります。
飲食や生活で意図せず潰れてしまった時
硬い食べ物、熱い飲み物、歯列矯正器具などによってつぶれてしまったケースでは、まずその原因となる刺激を取り除くことが早期改善につながります。その後、自分でつぶしてしまった時と同様に、清潔にして、栄養を摂り、休養し、市販薬などの対処を行い、痛みや治りの遅さ、再発を防ぎましょう。
口内炎を予防するための日常習慣
つぶすことを防ぐという意味でも、口内炎そのものを予防する日常習慣が非常に有効です。
栄養バランスを整える
粘膜形成に特に影響を与えるビタミンB群・C・亜鉛などを含む食品を意識的に摂取しましょう。偏食や外食ばかりの生活は避け、規則正しい食生活が重要です。
| 栄養素 | 主な食品 |
|---|---|
| ビタミンB2 | レバー、卵、乳製品、納豆 |
| ビタミンB6 | マグロ、カツオ、ニンニク |
| ビタミンC | ブロッコリー、キウイ、レモン |
| 亜鉛 | 牡蠣、豆、卵、ナッツ |
睡眠、休息、ストレスケア
睡眠不足や過度なストレスは免疫力が低下します。どうしても細菌感染しやすくなり、口内炎のリスクアップにつながります。適度な休息を取り、リラクゼーションや趣味時間の確保をしましょう。
正しい口腔ケア
毎日の歯磨きやうがいを習慣化しましょう。特に食後は重要です。柔らかめの歯ブラシを使用し、入れ歯や矯正器具使用者は定期的な調整を行いましょう。
口の中の物理的刺激を減らす
歯の尖りや、虫歯、入れ歯のガタつき、矯正器具の不適合などは慢性的な粘膜刺激となり、口内炎の発症や再発原因になります。早めに専門医でチェックをしてもらうのも大切です。
飲食、嗜好品の見直し
辛い物、熱い物、酸っぱい物、硬い物であったり、タバコやアルコール、砂糖過多などは粘膜に負担をかけやすいです。口内炎を作りたくない場合は、なるべく控えめにしましょう。
これらの習慣化により、口内炎ができて膨れてしまい、つぶしたくなるという悪循環を予防できます。
重症化する口内炎の受診タイミング
ほとんどの口内炎は、適切にケアすれば1~2週間程度で改善します。自己判断せずに歯科医院への受診をおすすめすることもある例を挙げていきましょう。
2週間以上たっても改善せず悪化している
同じ場所に何度も再発する
複数個できたり、サイズが大きい
黒褐色や不規則な形、出血やしこりを伴う
発熱、リンパ節の腫れ、原因となる刺激が思い当たらない
口内炎と思っていたものがつぶれてしまい、治りが非常に遅い
このようなサインは、たとえば口腔がんや白血病などの別の病気を示唆することもあるため、専門的な診断や治療が必要になることがあります。
まとめ
 口内炎をつぶすという行為には、早く何とかしたいという気持ちからつい手を出したくなりますが、実は多くのリスクを伴い、治癒を遅らせたり別の問題を招いたりする可能性があります。正しいケアは清潔に保つ、刺激を避ける、栄養、休息をとる、市販薬、貼りパッチを活用する、物理的刺激を除くという流れをまともに行うことが、口内炎を安全に早く治す近道です。長引いたり、繰り返したり、異常を感じる口内炎の場合はつぶしたから大丈夫と自己判断せず、早めの受診を心掛けましょう。
口内炎をつぶすという行為には、早く何とかしたいという気持ちからつい手を出したくなりますが、実は多くのリスクを伴い、治癒を遅らせたり別の問題を招いたりする可能性があります。正しいケアは清潔に保つ、刺激を避ける、栄養、休息をとる、市販薬、貼りパッチを活用する、物理的刺激を除くという流れをまともに行うことが、口内炎を安全に早く治す近道です。長引いたり、繰り返したり、異常を感じる口内炎の場合はつぶしたから大丈夫と自己判断せず、早めの受診を心掛けましょう。